ピカソと並ぶ20世紀最大の現代美術の巨匠フランシス・ベーコンの日本では30年ぶりとなる回顧展です。
ベーコンって、日本でどういう立ち位置にあったか、どういう評価のされ方をしてきたのか、詳しくは知りませんが、30年前の展覧会以降、ベーコンが日本でほとんど顧みられることがなかったことを考えると、人気も評価も決して高くなかったのではないかと思います。ちょうど30年ほど前、自分がアートにハマりだした頃、東近美で展覧会が開かれたのと前後していたということもあるのでしょうが、美術手帖などではよくベーコンが紹介されていました。ただその後、ベーコンが亡くなったときにいくつかの雑誌で特集や記事を読んだ覚えはありますが、それ以外にベーコンについて多く語られることはあまりなかった気がします。花村萬月の単行本でベーコンの絵を表紙に使ったなんてこともありましたが、ベーコンの伝記的映画『愛の悪魔』が公開されたときも、さして話題にもなりませんでした。
ベーコンの絵は、たとえばピカソの分かりにくさとはまた異なる分かりにくさがあります。その絵の気持ち悪さ、怖さ。決して美しくも、楽しくも、親しみやすくもない。そして一部ホモセクシャル的な描写への蔑視もあったかもしれません。海外では高い評価を得ていながらも、日本ではなかなか受け入れられませんでした。
本展は初日に拝見し、また“ベーコンナイト”なるイベントにも参加しましたが、若い人たちが大変多かったのが印象的でした。かつてイタリアの映画監督で同じく同性愛者を公言していたパゾリーニの回顧映画祭が開かれたときのことを思い出しました。長い間あれだけ日本で低く評価され、客が入らないといわれたパゾリーニが、ふたを開けたら予想を超える大盛況。あのときも観客の大半は若い人たちでした。こうした展覧会で若い、新しいアートファンにベーコンが紹介され、受け入れられることは感動的ですらあります。
フランシス・ベーコン 「スフインクス-ミュリエル・ベルチャーの肖像」
1979年 東京国立近代美術館蔵
1979年 東京国立近代美術館蔵
さて、今回の展覧会は33作品と出展数だけ見ると少なく感じられるのですが、その価値は総額数百億円という破格のものなのだとか。ここ数年のベーコンの作品価値の高騰は異常なほどで、ベーコンが展覧会の開催の困難な画家の一人といわれている所以でもあります。本展はそんな世界的に再評価されているフランシス・ベーコンの歩んだ軌跡を追いながら年代ごとにその作品を紹介しています。
1 移りゆく身体 1940s-1950s
現存する初期作品から画家として注目を集め始める1950年代までの作品を集めた最初のコーナーは、「こちら/あちら」「聖/俗」「スフィンクス」「ファン・ゴッホ」の4つのコーナーにさらに分けられています。
フランシス・ベーコンは1909年にアイルランドに生まれます。画家を志すまではいろいろとあったようですが、20歳のときにロンドンでインテリア・デザイナーの仕事をはじめ、ほどなくして油彩画を描き始めます。初期の作品はベーコンがことごとく破壊し、今ではほとんど残っていないといいます。その後の作品も、気に入らないものは買い戻してでも破棄したほど。生前ベーコンは、1944年以降の作品しか展覧会での展示を認めなかったそうです。
フランシス・ベーコン 「人物像習作 II」
1945-46年 ハダースフィールド美術館蔵
1945-46年 ハダースフィールド美術館蔵
ツイードのジャケットを着た半裸の男性らしき人が、シュロの葉の中に頭を突っ込んでいます。こちらに向けた顔は叫んでいるようにも見え、その後のベーコンの作品でたびたび登場する黒い傘が不思議な効果を出しています。一見、シュールレアリスムのようにも、それぞれのパーツが何か意味ありげにも見えますが、ベーコンが何を描き、何を訴えたいのか、まだどこか頭でっかちになっているようにも思えます。
フランシス・ベーコン 「人体による習作」
1949年 ヴィクトリア・ナショナル・ギャラリー蔵
1949年 ヴィクトリア・ナショナル・ギャラリー蔵
写真だと分かりづらいのですが、ベーコンの油彩画はとても薄塗りです。“ベーコンナイト”でキュレーターの保坂さんもおっしゃってましたが、ベーコンは絵は下手だけど、油絵の使い方はとても上手いのだそうです。本作は解説にはエクトプラズムが引き合いに出されていましたが、カーテンを開け、冥界に踏み込んでいるのか、ただ単にセックスをするため部屋に入っていくのか(もしくは出ていくのか)。1950年代頃までの作品にはこうしたボーッとした心霊写真的な、幻視的な作品が多くあります。
フランシス・ベーコン 「走る犬のための習作」
1954年頃 ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵
1954年頃 ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵
ベーコンは正式な美術教育を受けたことがなく、また著名な画家に師事したこともなく、ほぼ独学で油絵を習得します。ベーコンにデッサン力がどれほどあったのか分かりませんが、美術教育を受けていないことをコンプレックスに感じていたともいわれています。確かにベーコンの絵を観ていると、デフォルメ云々の前に身体のバランスの悪さが目に付くことがありますが、この「走る犬のための習作」は変に誇張することなく走るという動作や筋肉の動きを(ベーコンにしては)巧く捉えた珍しい作品です。まるで犬の亡霊が夜の町を徘徊しているようです。
フランシス・ベーコン 「叫ぶ教皇の頭部のための習作」
1952年 イエール・ブリティッシュ・アート・センター蔵
1952年 イエール・ブリティッシュ・アート・センター蔵
「叫び」はベーコンの一つの重要なキーワードで、ニコラ・プッサンの「嬰児虐殺」に描かれた叫ぶ母親の顔やロシアの映画監督エイゼンシュタインの「戦艦ポチョムキン」の有名なオデッサの階段のシーンで叫ぶ乳母などがそのイメージソースになっているといいます。また、本展で展示されていた「肖像のための習作」(2作品あり)に象徴されるように、ベーコンの描く人物の多くは囲いの中に閉じ込められていて、その中で叫ぶ姿からは、何か閉所恐怖症的な息苦しさや恐怖を感じます。
ちなみに、ベーコンの作品タイトルでよく「習作」というのがありますが、これは原題に「Study」という言葉が使われていて、特に準備段階の作品という意味での「習作」ではなく、完成された作品ということだそうです。
フランシス・ベーコン 「肖像のための習作Ⅳ」
1953年 ヴァッサー大学フランシス・リーマン・ロープ・アート・センター蔵
1953年 ヴァッサー大学フランシス・リーマン・ロープ・アート・センター蔵
ベーコンが無宗教だというのは有名な話で、キリスト教には深い興味を持っていなかったといわれていますが、ベラスケスの「教皇インノケンティウス10世の肖像」をモチーフにした作品を45点以上も制作しています。本作は、友人をモデルに人物像を描いていたところ、教皇の肖像へと変化してしまい、2週間で完成させた8作品の教皇像の内の一作だそうです。教皇は嘆き悲しんでいるのか、悩み苦しんでいるのか、はたまた叫びを上げているのか。イスにも囲いにも見える黄色の線は定規を使って引いたかのように真っ直ぐきれいなのに対し、教皇はまるで幽霊が消えていなくなる瞬間のように儚げです。解説によると、教皇とは最高位に当たる人間、つまり“父”なる存在であり、ベーコンはそれに対し「因習的な良識や価値観の転覆」を狙ったのではないかとありました。ベーコンと実父の関係が複雑であったことからも、“父殺し”を読み解く批評家もいるようです。
フランシス・ベーコン 「スフインクスⅢ」
1954年 ハーシュホーン美術館蔵
1954年 ハーシュホーン美術館蔵
ベーコンはエジプト旅行で受けた印象をもとにスフィンクスを主題とする作品を残しています。本展では1953~1954年に描かれた作品4点の内3点が展示されています。この時代のベーコンの作品同様、半透明の、スフィンクスなのか人物なのか(もしくは合体か)不明確さがあります。後年描いた「スフインクス-ミュリエル・ベルチャーの肖像」は女性とスフィンクスが正しく合体されていたりします。ミュリエル・ベルチャーはベーコンが通った“コロニールーム”の女主人で、男勝りで威厳のある女性だったとされ、ベーコンにとってはスフィンクス的な存在だったのかもしれません。
フランシス・ベーコン 「ファン・ゴッホの肖像のための習作Ⅴ」
1957年 ハーシュホーン美術館蔵
1957年 ハーシュホーン美術館蔵
「ゴッホは誰よりも重要な存在」とベーコンが語っているように、彼はゴッホに強い影響を受け、またゴッホの絵をモチーフにした作品も手がけています。本展ではその内の2点が展示されていました。この「ファン・ゴッホの肖像のための習作Ⅴ」の基となったゴッホの「タラスコンへの道を行く画家」は残念なことに第二次世界大戦で焼失してしまったそうで、ベーコンは写真を見て本作を描いたようです。
こうしたゴッホのオマージュ的作品はベーコンの転換期となり、ベーコンの作品に色彩感が強まり、より明るい色を使うようになります。また、比較的薄塗りだったものが部分的に厚く塗られたり(それでもそんなに厚くない)、筆のタッチも荒々しいところを感じるようになります。この時期以降、さらに薄塗りと厚塗りの配置、その塗り方(指で塗ったり、布を使ったり、絵具に砂を混ぜたり、時に絵具を投げつけたりもする)、色の選び方が絶妙になり、偶然性を超えた天分をその作品から強く感じようになります。
会場の途中にはフランシス・ベーコンのドキュメンタリーの3分ほどのダイジェスト版が流れています。
2 捧げられた肉体 1960s
世界的に注目されるようになったベーコン。これまでの作品とは大きく印象が変わる1960年代の作品を展示しています。
フランシス・ベーコン 「ジョージ・ダイアの三習作」
1969年 ルイジアナ近代美術館蔵
1969年 ルイジアナ近代美術館蔵
1964年以降、ベーコンは主題のひとつとして頭部をメインに描いた作品を発表するようになります。ジョージ・ダイアは元“こそ泥”で、ベーコンのアトリエに盗みに入ったことがきっかけで肉体関係を結んだといわれる恋人。10年近い恋愛関係の末、1971年10月、パリのグラン・パレでの大回顧展の開幕直前にパリのホテルで自殺(ドラッグの過剰摂取による中毒死とも)します。本作はそんな二人の関係を物語るように、どこか暴力的で、破壊的で、激しい感情が強く込められているかのようです。醜く歪んだその姿からは恋人への賛美を見出だすことすら困難です。しかし、ダイアはベーコンの作品のモデルとして、またアイコン的存在として、最もイマジネーションを掻きたてたとされ、ダイアの自殺後もベーコンは彼をモチーフにした作品を描き続けます。
ベーコンとダイアの愛憎入り混じった関係はジョン・メイブリー監督のイギリス映画『愛の悪魔/フランシス・ベイコンの歪んだ肖像』に詳しいので、ぜひご覧ください。ベーコン・ファンは必見です。
フランシス・ベーコン 「裸体」
1960年 フランクフルト近代美術館蔵
1960年 フランクフルト近代美術館蔵
ベーコンが描く人物はほとんど男性で、女性を描いたものは少ないそうで、本作はその珍しい例として紹介されていました。全裸の女性が挑発的なポーズをとった一見官能的ではありますが、顔は相変わらず崩れ、ソファー(?)で誰かを誘うような動作はどこか痛々しくもあります。本作はマティスの絵の影響も指摘されています。
3 物語らない身体 1970s-1992
1971年のグラン・パレでの回顧展は大成功を収めますが、ダイアの死の影響なのか、その後の恋人の影響なのか、1970年代のベーコンの作品は複雑化し、その画風に変化が生じます。ここでは1970年代以降、最晩年までの作品を追います。
1970年代以降に特に増えるのが大型の三幅対(トリプティク)で、この章の会場は三幅対を中心に構成されていました。三幅対は祭壇画などキリスト教絵画でよく見られる形式ですが、ベーコン自身はフランスの映画監督アベル・ガンスのサイレント映画で、3面のスクリーンに異なる映像を映した大作『ナポレオン』を観て思いついたとも語っています。三幅対の一幅がそれぞれ縦約2m横約1.5mなのは、ベーコンのアトリエの大きさに準じた大きさなのだそうです。
フランシス・ベーコン 「三つの人物像と肖像」
1975年 テート蔵
1975年 テート蔵
三幅対ではありませんが、一枚のキャンバスに3つの人物(というより最早フリークス的クリーチャー)を描いた作品。左側の人物はジョージ・ダイアとされていますが、右側の背中をこちらに向けた人物や下側の歯をむき出しにした肉塊(解説によるとギリシャ神話で神の裁きを伝える復讐の女神)は見た目は誰か何か分からず、またそれぞれがとても複雑で不可思議な動きをしているのが特徴的です。映画評論家の滝本誠氏がベーコンの作品を“肉の心理的風景”と評していましたが、まさにそんな感じです。私たちは描かれた対象物やその動きに意味や共通点を探し、何かしら理屈を語りがちですが、それさえも拒む、というより意味のない行為にしてしまうところにベーコン作品の面白さがあるような気がします。それがさらに観る者の好奇心を掻き立てるわけですが。
フランシス・ベーコン 「三幅対」
1991年 ニューヨーク近代美術館蔵
1991年 ニューヨーク近代美術館蔵
男性の下半身に顔写真を切り貼りしたような奇妙な肢体。右側にはベーコンの顔が、左側には当時の(最後の)恋人ともベーコンの友人ともアイルトン・セナともいわれる男性の顔が描かれ、それぞれ片足を暗闇の中に踏み入れています。真ん中には絡み合うような肉体の塊り。逞しい脚や露な男性器から性的なメッセージも強く感じさせます。同じような黒の矩形を描き込んだ三幅対は他にも多く存在しますが、この作品はベーコンが亡くなる数ヶ月前に描かれた作品ということもあり、向こうの世界、つまり“死”と関連づけて考えられてもいます。
本展の展示作品数は決して多くありませんが、それぞれの作品に圧倒的な力があり、作品数の少なさを全く感じさせません。作品が少ないから、あまり時間がかからないかと思いきや、会場を出たときは2時間近くも経っていました。これだけまとまった数のベーコン作品を観られる機会はそうはないと思います。数年後には語り草になるような展覧会じゃないでしょうか。フランシス・ベーコンの美しい毒にあたってみるのも悪くないと思います。
【フランシス・ベーコン展】
2013年5月26日(日)まで
東京国立近代美術館にて
![芸術新潮 2013年 04月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51i-qygBlwL._SL160_.jpg) 芸術新潮 2013年 04月号 [雑誌]
芸術新潮 2013年 04月号 [雑誌]![美術手帖 2013年 03月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NI9eq5GqL._SL160_.jpg) 美術手帖 2013年 03月号 [雑誌]
美術手帖 2013年 03月号 [雑誌] わが友フランシス・ベイコン
わが友フランシス・ベイコン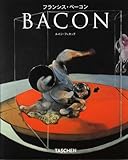 フランシス・ベーコン BACON
フランシス・ベーコン BACON![愛の悪魔(トールサイズ廉価版) [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51TWZ5FXAXL._SL160_.jpg) 愛の悪魔(トールサイズ廉価版) [DVD]
愛の悪魔(トールサイズ廉価版) [DVD]












ght5er375
返信削除golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet
golden goose outlet